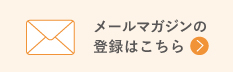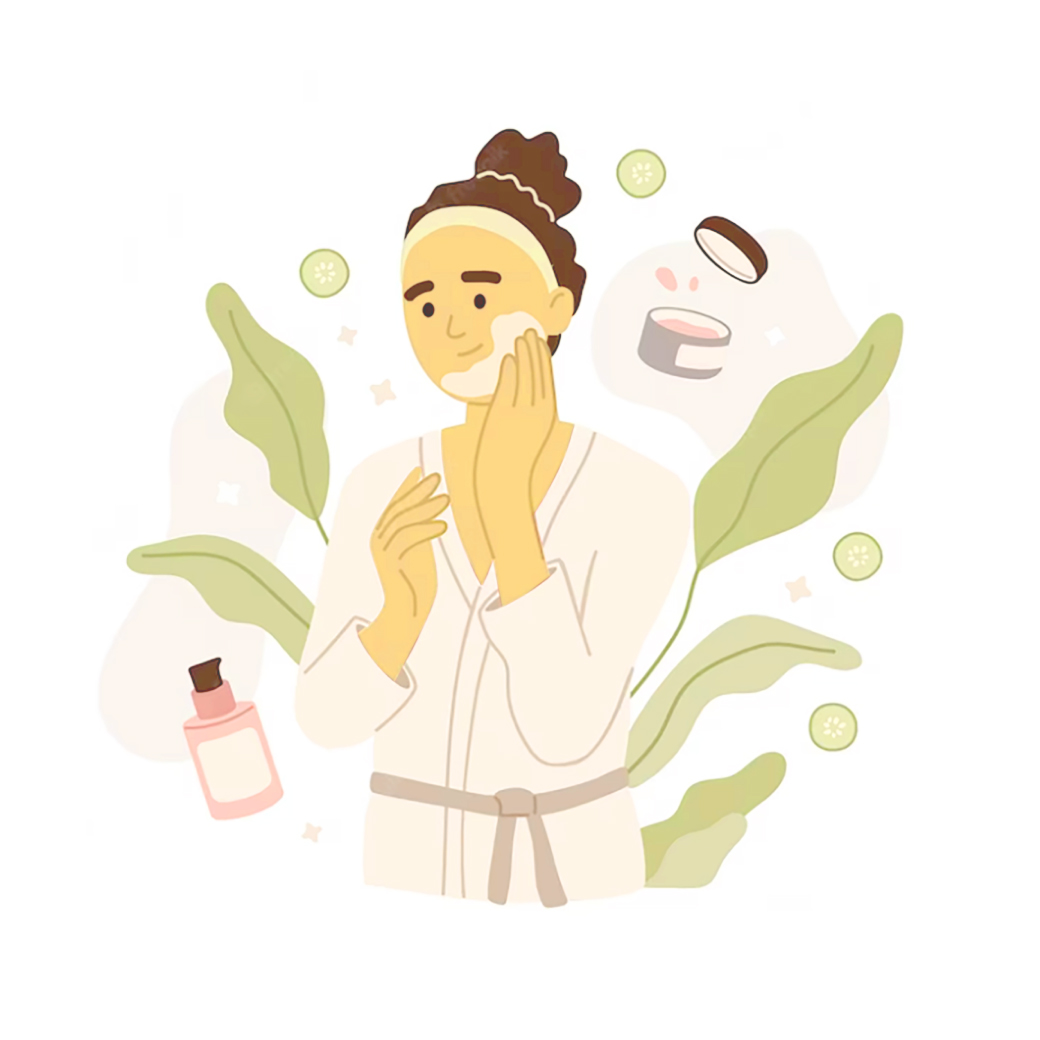風邪でも花粉症でもない…ひょっとして「寒暖差アレルギー」!?
SUMMARY
- ・「寒暖差アレルギー」は気温差によって起きる鼻炎の一種
- ・症状が出やすい人とそうでない人がいるのはなぜ?
- ・栄養バランスを整えて、ストレスをためないこと
- ・まとめ
寒さもいよいよ本番です。皆さま、毎日温かくお過ごしでしょうか?
温かい格好をしているのに、外に出るとくしゃみや鼻水がとまらなくなる…そんな経験をされたことはありませんか?
風邪でもないし、花粉症でもない…という方は「寒暖差アレルギー」の可能性があります。
いわゆる普通のアレルギーとは異なる「寒暖差アレルギー」とは? 症状や原因、対策を橋本知子先生に伺いました。
「寒暖差アレルギー」は気温差によって起きる鼻炎の一種
「くしゃみや鼻水などは、鼻炎のひとつですが、アレルゲンがはっきりしているのがアレルギー性鼻炎。主に花粉やダニ、ハウスダストが原因でアレルギーを起こします。症状としては鼻水やくしゃみのほかに、目のかゆみや充血なども現れる場合が多いですね。またくしゃみや鼻水とともに熱がある場合は、風邪を疑ったほうがよいでしょう」と橋本先生。
その一方で同じようにくしゃみや鼻水、鼻づまりがあるのに、目のかゆみや熱がない場合もあります。それが「寒暖差アレルギー」です。
「『寒暖差アレルギー』は、7度ほどの温度差があると起こりやすいといわれている症状です。気温差が刺激となって鼻粘膜の血管を広げ、内部が腫れることによってくしゃみや鼻水などの症状を引き起こします。アレルギーと名前がついていますが、病院でアレルギーの検査をしてもアレルゲンは何も検出されず、実際はアレルギーではありません。医学的には『血管運動性鼻炎』と呼ばれています」
特に冬になると室内外の気温差によって「寒暖差アレルギー」の症状が出てくる人が多くなる傾向に。でも夏も冷房の効いた部屋と外気の温度差がありますが、あまり「寒暖差アレルギー」の人は見られません。
「気温差というところからいうと、年中起こってもおかしくないとは思います。ただ乾燥することによって症状が出やすくなるので、湿度の低い冬によく見られるのでしょう」
症状が出やすい人とそうでない人がいるのはなぜ?
同じ環境下でも「寒暖差アレルギー」が出る人と、そうでない人がいます。その差はどこにあるのでしょうか?
「実は日常生活が大きく関わっています。時間が不規則な人、食事の栄養バランスが悪い人、運動不足の人…そういった方は症状が出やすいですね。自律神経のバランスの乱れも原因の一つかもしれません」と橋本先生。
特に慢性的に疲れがたまっている人やストレスが多い人は要注意。
「多忙な日々を送っていたり、乱れた生活習慣などのストレスによってビタミンCは大量に消費され、
そのほかのビタミンやミネラルも不足してしまいます」
栄養バランスが悪いと粘膜も弱くなってしまいます。食事も重要なキーワードになってきそうです。
栄養バランスを整えて、ストレスをためないこと

日々を快適に過ごすために、規則正しい食生活とストレス解消が大きな鍵に。特に食事では、栄養バランスを整える栄養素をしっかりとることが大切です。
「亜鉛、ビタミンD、ビタミンA、ビタミンC、たんぱく質をとれる食事を心がけましょう。できれば食品からとるのがいちばんですが、消費の激しいビタミンCなどはサプリメントでも補いたいもの。必要量は個人や体調によって異なりますが、忙しい日々が続いている場合にはいつもより多めに飲むことをおすすめします」
そして自分なりのリラックス方法をみつけることが大切。
「ストレスをなくすことはできないと思いますので、解消する方法をもっておくとよいでしょう。おすすめは入浴です。体を温めてリラックスすることで自律神経も整えることができ、『寒暖差アレルギー』対策にもなります」
まとめ
症状がつらいときは、専門家に相談し対症療法もできますが、健康の土台となる毎日の食生活をきちんと整えることが基本になります。もちろん外出される際は、マフラーや手袋などでしっかり防寒してくださいね。 
橋本知子先生
臨床分子栄養医学認定指導医。高濃度ビタミンC点滴療法認定医。自信の乳がんきっかけに分子栄養学に出合う。クリニックでは分子栄養学的な検査やカウンセリングを行い、病院に行くほどではないけれど不調をかかえている患者の治療にあたっている。