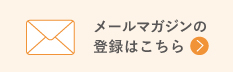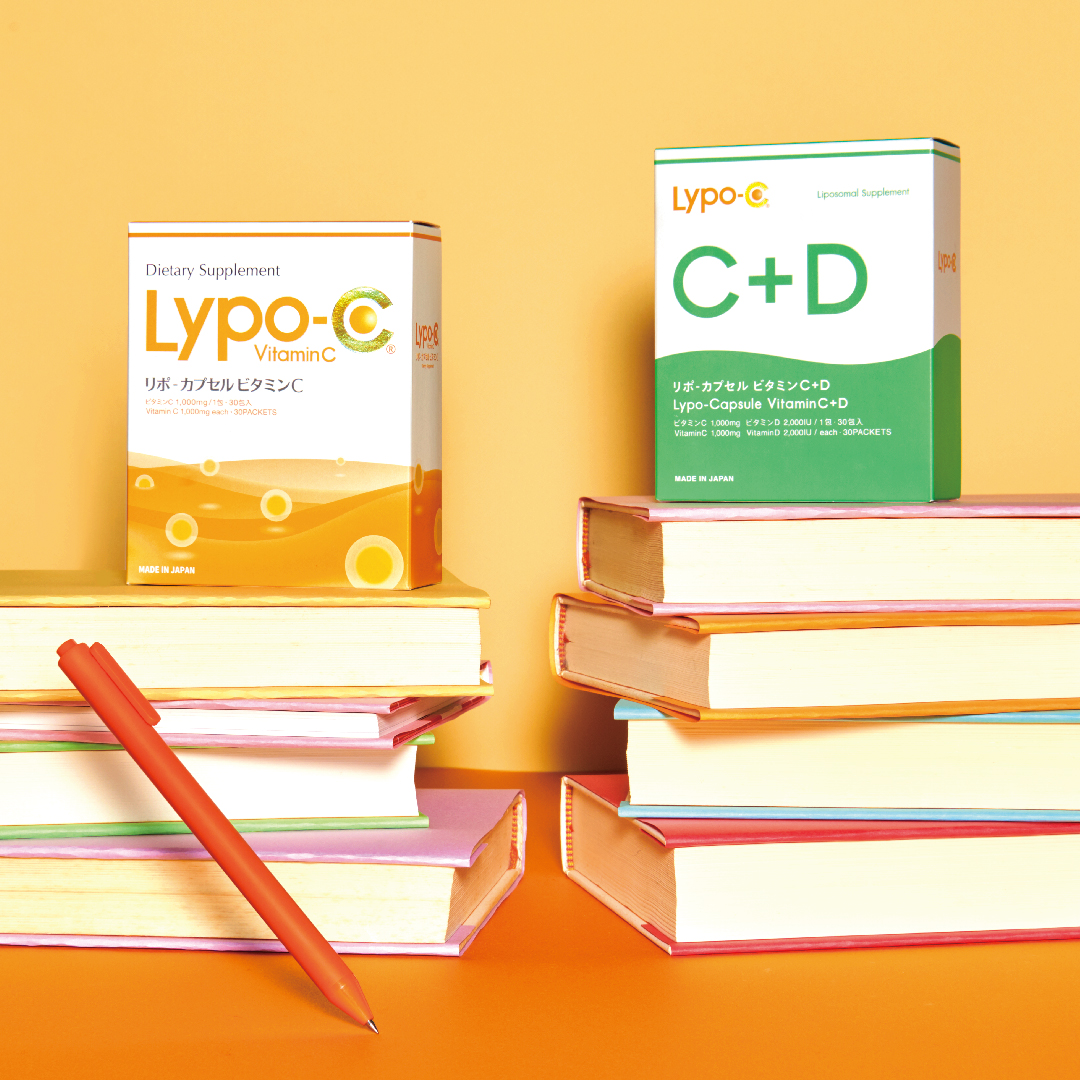睡眠の質を上げる|良い睡眠のメリットや質を上げる方法とは?
SUMMARY
- ・質の良い睡眠とは
- ・睡眠の質を上げるメリット
- ・睡眠の質を下げてしまう原因
- ・睡眠の質を上げるためには
- ・まとめ
寝ても疲れが残っていると感じたり、長時間寝たのにスッキリしなかったり、これらの原因は睡眠の質が悪くなったことによるものかもしれません。
睡眠不足や疲労による、日中のパフォーマンス低下やメンタル不調からくる病気を避けるためにも、睡眠の質を上げる方法を知り、実践してみることをおすすめします。
質の良い睡眠とは
睡眠の質を測る指標の一つに、睡眠休養感があります。
これは、睡眠によって休養できたと感じる状態のことです。
睡眠休養感は、睡眠の量だけでなく、睡眠環境や生活習慣などからも影響を受けます。
また、人間の睡眠状態には、身体を休めるレム睡眠と脳を休めるノンレム睡眠があり、睡眠休養感を得るには、レム睡眠とノンレム睡眠の周期バランスが重要です。
睡眠の質を上げるメリット
睡眠の質を上げると、日中に溜まった心身の疲れが取れやすくなることや、免疫機能を向上させ病気の予防や健康維持につながることなどが分かっています。
ここでは、睡眠の質を上げるメリットを説明します。
● 疲労回復の効果がある
質の良い睡眠は、心身の疲労回復に役立つでしょう。
人間は自律神経のバランスが崩れると、交感神経と副交感神経の切り替えが上手くいかず、常に交感神経が刺激されることで緊張状態が続き、ストレスや疲労を蓄積します。
質の良い睡眠をとることで、脳の緊張状態を解き、副交感神経の機能を高めることが可能です。特にノンレム睡眠は副交感神経が優位になり、疲労回復につながります。
睡眠を上手に利用して、自律神経を整え翌日に疲れを残さないようにしましょう。
● ストレス解消の効果がある
睡眠には、脳を休める効果があるためストレス解消にも効果的です。
睡眠中の脳は、視覚や聴覚の情報を制御して、日中に入ってきた情報を処理しています。
必要な情報だけを記憶して、不要なものは消去する、情報の整理・記憶保存・消去を行っています。
この作業によって知識の定着やストレスの除去をしているのです。
また、睡眠不足は疲労感や情緒不安定、判断力の低下などを引き起こし、生活の質に悪影響を及ぼします。
質の良い睡眠によって、ストレスの原因自体を減らし、溜まってしまったストレスは除去することで、総合的にストレス解消ができます。
● 免疫機能の向上・健康維持
睡眠と免疫機能には深い関係があると言われ、質の良い睡眠は風邪や感染症予防に効果的です。
また、適切な睡眠時間をとることで生活習慣病やうつ病の発症リスクが低いことも分かっています。
これらの効果を最大にするには、食事や運動などの生活習慣と同じように、日々の積み重ねが重要です。
質の良い睡眠は、日中の過ごし方にも変化をもたらします。
日中を活発に過ごせることで、スムーズな入眠や熟睡につながる好循環を作ります。
● 肥満防止・美肌効果
睡眠時間が短くなると、食欲を抑えるレプチンというホルモンの分泌が減少し、反対に食欲を増進させるグレリンというホルモンが増加することがわかっています。
質の良い睡眠を取ることは、ホルモン分泌のバランスを整え、肥満防止に役立つでしょう。
また、ノンレム睡眠の間、新陳代謝の向上や細胞の修復を促す成長ホルモンの分泌が高まります。
成長ホルモンの分泌は、肌ツヤの改善や皮膚のターンオーバー促進などの効果が期待できます。
さらに夜に分泌量が増えるメラトニンには、睡眠のリズムを整えるためだけでなく、活性酸素を除去する効果があり、アンチエイジングにも効果的です。
睡眠の質を下げてしまう原因
睡眠の質を高めるためには、寝る前までの習慣や日々の過ごし方に注意しておくことが大切です。
何気ないナイトルーティンが、睡眠の質を下げてしまう原因となることもあるでしょう。
ここでは、睡眠の質を下げてしまう原因を具体的に解説します。
● 生活習慣の乱れ
入眠前の飲酒や喫煙、熱いお湯での入浴などの習慣は、交感神経を刺激し睡眠の質を下げてしまうおそれがあります。
睡眠の質を意識する前に、生活習慣を見直し正すことが必要です。
寝る直前の脳が覚醒してしまうような習慣は、睡眠の質も下げてしまうでしょう。
夜眠くなり朝目が覚めることは、人間に備わっている体内時計の働きによるものです。
身体に備わっている体内時計が不適切な生活習慣によって乱れ、睡眠の質を低下させてしまいます。
● ストレス
仕事やプライベートの悩みや不安など、心理的なストレスも睡眠の質を下げてしまう原因のひとつです。
強いストレスは、自律神経を乱すことが予想されます。
ストレスを感じると交感神経が活発になりやすく、寝つきが悪くなってしまったり、睡眠途中で目が覚めてしまったりと悪影響を及ぼすことがあります。
「眠れない」ことを意識し過ぎるのも、心理的なストレスになってしまうでしょう。
質の良い睡眠には、副交感神経が優位なリラックスした状態で眠ることが大切です。
● 睡眠の環境
寝室の明るさや温度、湿度、騒音などの環境や身体に合う寝具が整っていない場合にも、睡眠の質を下げてしまう恐れがあります。
睡眠に大切な環境は、適切な「光・温度・音」です。
寝床につく約1時間前からは、部屋の明かりを少し暗くし落ち着いて過ごし、寝室は静かな環境で適温になるよう調節しましょう。
寝る前にスマートフォンやテレビなどを見て、ブルーライトを浴びてしまうことも睡眠の質を低下させる原因のひとつです。
睡眠の質を上げるためには
睡眠の質を上げるためには、自身の習慣や周りの環境を整えることが大切です。
可能な範囲で少しずつ状況に適した対策を取り入れて、睡眠の質を高めましょう。
ここでは、睡眠の質を上げるための方法を紹介します。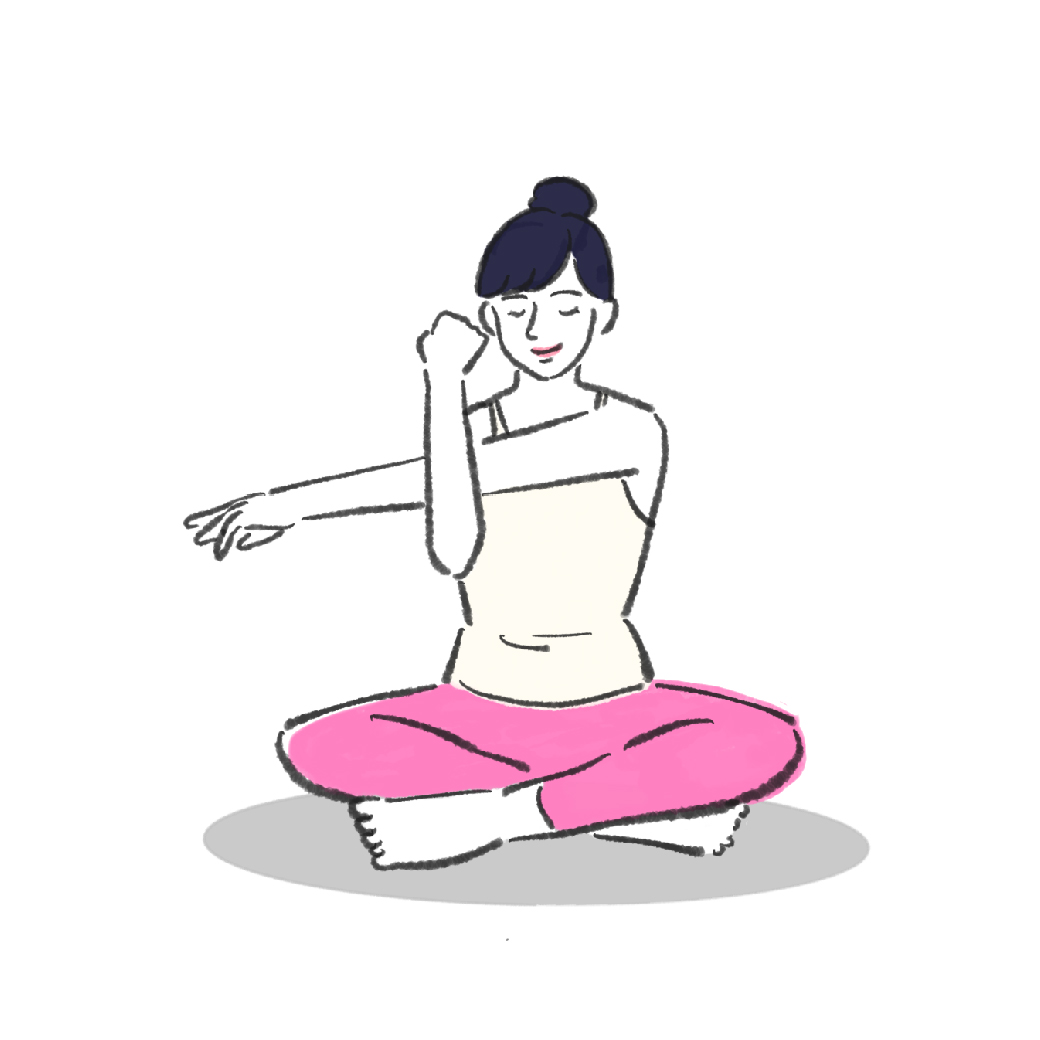
● 食生活を整える
朝食をしっかり摂るようにしましょう。
朝食を摂ることは、体内時計のリセットに役立ち、遅寝・遅起きを防ぎます。
また、規則正しい時間であっても、夕食は睡眠の2時間前までにし、遅い時間に食事を摂ることは控えるとよいでしょう。
睡眠直前の食事や消化に時間がかかる食べ物は、胃腸が活発に動いてしまい睡眠が妨げられてしまいます。
● 適度な運動習慣をつける
日中に体を動かして適度な疲労を感じることは、夜間の深い眠りにつながります。
適度な運動習慣は睡眠休養感が得られることが分かっているためです。
特に、ジョギングやウォーキングのような有酸素運動や、ダンベルを用いた筋力トレーニングなどが睡眠の質を高めるといわれています。
運動の時間や回数は、こどもであれば強度の高い運動をできるだけ毎日60分以上、成人であれば中強度以上の運動をできるだけ長く、高齢者であれば低中強度の運動を週に数回60分未満が目安です。
● 入浴
38〜40℃のぬるま湯につかり、体を十分に温めてリラックスした状態を作ると、質の良い睡眠に効果的です。
入浴によって体温が一時的に上がり、下がったタイミングで眠たくなるため、入眠を促します。
時間としては、布団へ入る2〜3時間前に入浴すると、体温が下がるタイミングと合うため、深い睡眠が得られやすくなるでしょう。
また、入浴剤を活用するとよりリラックス効果が得られます。
好きな香りや期待する効果で選ぶと、より睡眠の質が上げられるでしょう。
● 朝日を浴びる
朝日を浴びると体が目覚めて体内時計を調整し、睡眠のタイミングに合わせて眠りやすくなります。
起床後にカーテンを開けて朝日を浴びる習慣は、体内時計をリセットして、日を浴びてから15〜16時間後に眠気を起こすためです。
目覚めをよくするポイントは、起床直後に朝日を浴びることです。
起床直後でない場合には、眠気の起きるタイミングがズレるため、だんだんと寝る時間が遅くなり夜型の習慣へシフトしてしまう恐れがあります。
● 睡眠の環境を整える
前述にもある通り、寝室の温度や湿度、光、音などの環境を季節に応じて自分に合うように整えることは、睡眠の質を上げることにつながります。
音は静かであることが適していますが、全くの無音で不安感が出てしまうようなら小さな音でヒーリング効果のある音楽を流すとよいでしょう。
枕やマットレスなどの寝具も自分に合った高さや硬さのものを選んでみてください。
後頭部から首にかけてのS字カーブを保つようにして、立ち姿に近い状態になることが望ましい寝姿です。
まとめ
質の良い睡眠を取るためには、日々の生活習慣やストレス、寝室の状態を整えることが大切です。
睡眠の質が下がってしまうと日中の活動の低下やうつなどの病気にもつながりかねません。
セルフケアをし、それでも睡眠不足や疲労を感じる場合には、一度医療機関で受診するとよいでしょう。
記事監修

吉井友季子
吉井クリニック
大阪市立大学医学部卒業、大阪市立大学附属病院第一外科勤務の後、大阪江坂の吉井クリニックを開院。
現在は、吉井クリニック院長、医療法人優美会理事長を務める。
美容と健康をトータルにサポートするクリニックをコンセプトに診療を行っている。婦人科疾患の早期発見、早期治療や美容医療だけでなく、人間ドックや内科診療、禁煙外来や睡眠時無呼吸症候群など、生活習慣病の治療にも幅広く力を入れている。